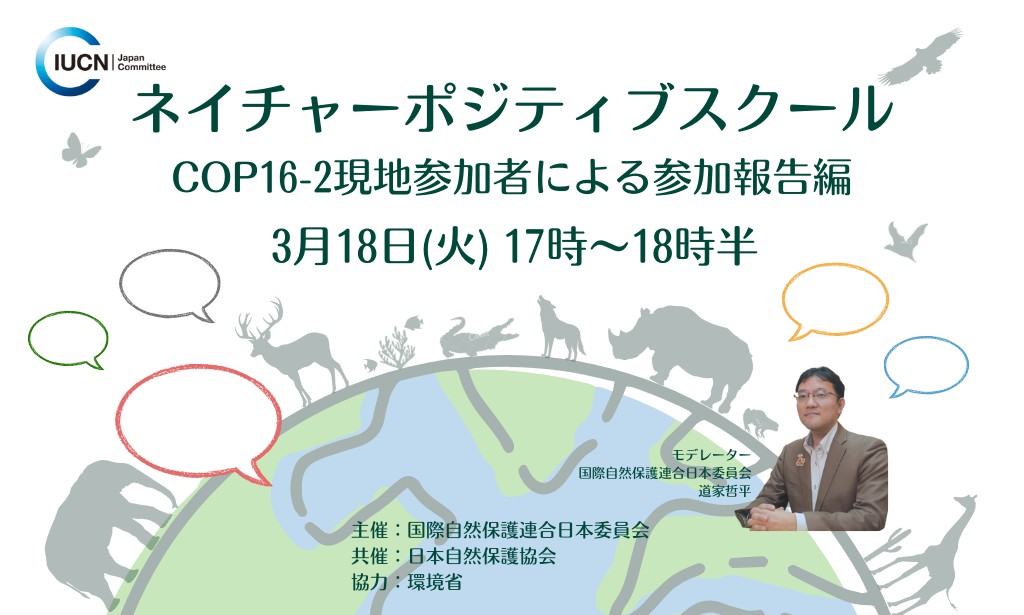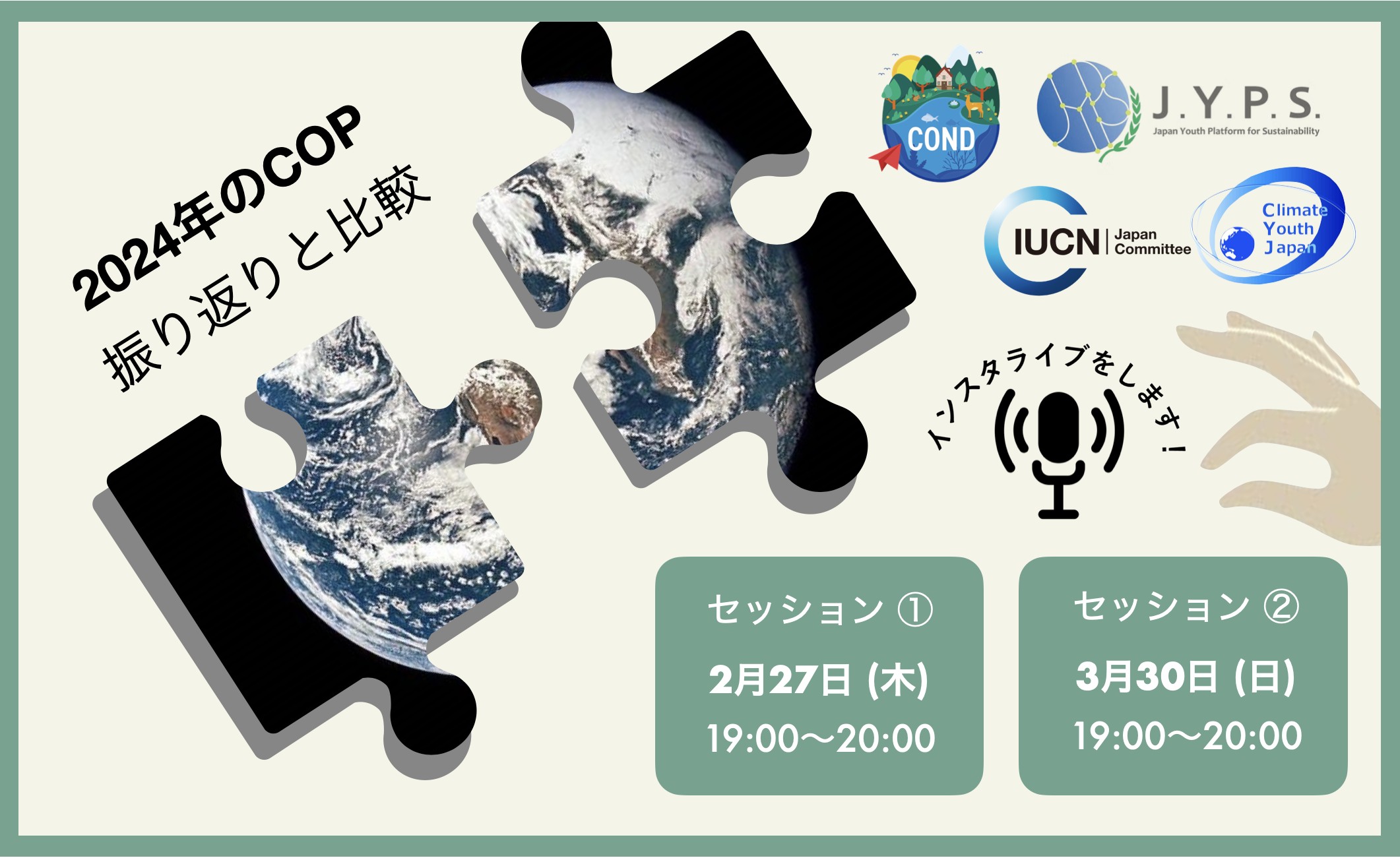コロンビア・カリ、COP16最終日の夜12時。議題14が採択され、会場内で大きな歓声が上がった。先住民地域の作業部会(WG)の常設化(Subsidiary Body on 8(J))が決定された、歴史的な瞬間だった。
写真は議題14が採択された瞬間である(出典:https://flic.kr/p/2qrDg7U)。これは何を意味するのか、その重要性と意義はなんだろう。
生物多様性条約(CBD)は、世界の生物多様性の保全、持続可能な利用、そして遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分という3つの目標の下、1992年のリオ地球サミットに向けて誕生した。先住民地域共同体は、生活が生物多様性に依存していると同時にその生活と自然を守ることが一体となっているセクター(いわば重要な管理者)であるにも関わらず、先住民の役割はCBDの様々な決定に反映されるまで、長い時間を要した。 COP 15で、昆明・モントリオール生物多様性枠組(KMGBF)が採択され、23のターゲットのうち6つのターゲットに、様々な形で先住民族に関して言及されているのは、その意味でとても大きな進展だった。しかし、言及されればよいというだけでは勿論ない。
23のターゲットの中で、先住民地域共同体が最も懸念している一つは、ターゲット3(30by30目標):陸と海のそれぞれ少なくとも 30%を保護地域及び OECM により保全する、というものである。KMGBFでは先住民が伝統的に利用してきた土地を独自な保全地域としてではなく、OECMに分類している。
「保護地域」は、1980-90年代に面積を急速に拡大する過程で西洋的な自然保護の観念から、先住民地域共同体の伝統的利用も含めて自然資源の採取を規制したり、政府の都合で壁や境界線を引くこともあるなど、時には暴力や搾取、人権侵害につながることもあった。このような自然保護を「fortress conservation(要塞型保全)」と呼ぶことがあり、『人間は自然から切り離された存在である』、あるいは『自然の外にいる存在である』という認識から生まれた手法として考えられている。こうした人と自然の関りに関する思い込みは、人間の存在は自然や”純粋”な生態系を破壊するもので、生物多様性と自然を守るためには人間の存在をその地域から”完全に”除外しなければならないという保全の考え方につながってきた。その結果、先住民コミュニティから土地を奪い、立ち退かせるということにつながったのだろう。
今後、30by30目標を達成するために、世界各地で保護地域を増やすことが必然となる。自然保護の「難民」(conservation refugee)の歴史を経験した先住民共同体が、ターゲット3及びKMGBFを疑問視し、警戒するのは致し方ない。
国際交渉の場において、先住民族はオブザーバーで国の代表ではないため、発言機会は国が一通り発言した後にしか回ってこない。また、先住民族に関する従来の作業部会(WG)は、常設ではない(暫定のadhoc)会合であったため、WGをやるかどうかは、いちいちCOPの決定を待たなければなかった。その場合、例えば中期的に話し合うべき課題でも二つ先のCOPの議題を定めることができず、計画的な議論がされてこなかった。さらに、CBDにおける理解は進んできたが、先住民族あるいは地域共同体の多様な伝統、慣習、そして様々な歴史的かつ文化的文脈があるにもかかわらず、「Indigenous People and Local Communities」というただ一つのカテゴリーに括っていることへの違和感は「自然と文化サミット」などでも度々耳にした。 常設化はこれを変える「象徴」的決定として、先住民地域共同体が熱望していた。
確かに、今回の決定である第8(j)条(Article 8(j))は、締約国に先住民地域の伝統的な生活様式、慣行と知識を尊重、保存、維持しすることを要求していて、非常に良い文章に見える。しかし、第8(j)条の冒頭には「subject to national legislation(自国の国内法に従う)」という一句が入っている。国内法がない場合は、締約国の義務が軽くなるようにも解釈され、第8(j)条は拘束力が弱く、その推進が各国の判断に委ねられているとも解釈できる。
今後はCOP 16で採択された先住民地域の作業部会の常設化によって、より計画的な検討をGBFという大枠のなかで行うことが期待される。この決定によって、先住民の土地権利は認められるようになるのだろうか、それとも、単なる象徴的な作業部会になるだけなのか。Subsidiary Body on 8(J)の設立はゴールではなく、最初の一歩であろう。

2024 年10月26日に開催されたCOP16ネイチャー・カルチャーサミットで先住民の土地権利の重要性を訴える先住民の女性
サン パトリシア
筑波大学世界遺産学学位プログラム